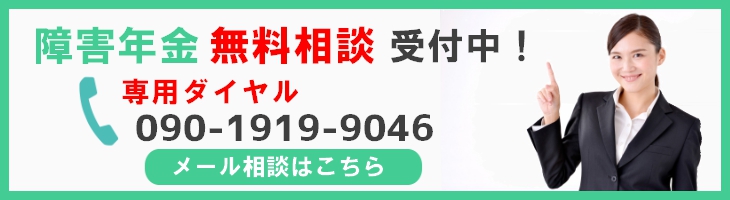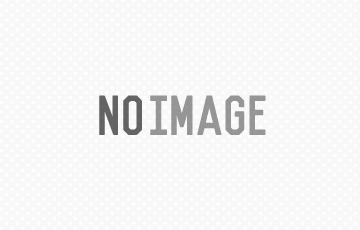申請者が障害年金を受給するには、「加入要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」を満たしていることが前提です。
障害年金請求申請時のポイント
障害年金の請求では、
- 「初診日」に年金制度に加入していたか(加入要件)
- どの年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していたか
が重要です。
「初診日」において国民年金に加入していた場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
厚生年金に加入していた場合は、障害等級が1級、2級、3級に該当すれば受給場合があります。
「障害認定日」をどの時点に設定するのかで、受給できる年金額にも差が出ます。
初診日から1年6ヶ月時点に設定するのか・・・
「事後重症」で請求するのか・・・
一番多く受給できる日を設定するのがポイントです。
診断書について
障害年金の受給要件の一つに「障害状態要件」があります。
障害年金申請時に 「私には障害があり、日常生活に支障が生じています!!!」ということを専門家として証明するのが医師の「診断書」 であります。
そして、この「診断書」によって障害年金の受給だけではなく、認定等級にも影響を与えますので、担当の医師とはよくコミュニケーションを取り、記入してもらう必要があります。
障害年金を申請された方の不満の声として上がるのは、
「医師に書いてもらった診断書が、実際の症状よりも軽く書かれていた!」
ということがよくあるようです。
この原因としては、担当医に上手く日常生活での苦悩が伝わっていなかったという事が考えられます。
また、 障害年金を申請するための「診断書」の書き方を知らない医師が多い という事も考えらます。
このように、「診断書」の内容一つで、受給できる年金額が減ることもあるのです。
もちろん、書いて頂いた「診断書」を確認後に、改めて訂正をお願いするということも不可能ではありません。
障害年金の認定方法について
障害年金の裁定請求書(申請書)が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているかを確認されます。
最寄りの年金事務所へ裁定請求書(申請書)を提出した場合、年金事務所が内容を確認し、受給資格があるかを確認します。
その後、障害の状態を認定医が診断書などの添付資料から客観的に判断します。
障害等級の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめ、その等級を決定します。